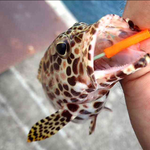2017年04月23日
群れている魚は、単独で泳いでいる魚よりも釣れにくい?
「魚は合意によって彼らのリーダーを選ぶ」(https://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081113140310.htm)
↑の記事を参照しました。
まとめると、
【判断をするとき、群れが大きいほうが、小さいほうに比べ、正しい判断をする】
ということが書いていると思います
※(Google翻訳で翻訳し、それを私が翻訳したので、間違って解釈しているかも知れません。)
原文は、 https://www.sciencedaily.com/releases/2008/11/081113140310.htm です。
↑の記事では、写真にガーラが載ってますが、
この実験でつかわれたのは、「トゲウオ」といい
日本本土にすむ「イトヨ/トエヨ」に近い魚らしいです。
 下が、一応グーグル翻訳をして、すこし手を加えた日本語の文章です。
シドニー大学のアシュリーワード(Ashley Ward)氏は、「トゲウオの群れはより小さな先導者(群れの方向を決める魚)よりも大きい先導者に従う傾向があることが判明しました。実際に私たちの目を惹いたのは、ある種の社会的フィードバックメカニズムによって、群れの規模が拡大するにつれて、このような傾向が高まったことだ」と語った。
ウプサラ大学のDavid Sumpter教授は、「彼らの合意は簡単なルールによって生まれる。 「ある魚は正しい方向に進む。しかし、それと同時に間違いを犯して間違った方向に進む魚もいる。まだ、意思が決まっていない魚は、数の多いほうへ進む。そうやって、一方の道に魚の数が多くなり、残りの魚は数の多いほうへついていく」
⇒つまり、①先導者⇒②先導者を判断する魚⇒③後ろのほうの魚
の順で、群れは方向を決めながら進んでいくということでしょうか?
魚は意思決定を行うときに、前の魚の意思決定を参考にする?
Sumpterは、「全体の意思決定」とは、ひとりひとりの意思決定から決定されて、できる限り効果的にその意思を満たすための意思決定である。 「通常、私たち自身の意思決定について話すとき、誰もが行動の過程についての証拠を提示することが許され、意思決定者が意思決定者の一般的意見を反映するならば合意に達すると我々は言う。これは、1人または非常に少数のグループメンバーによる意思決定とは対照的です。グループメンバーは、自分の意見だけを反映する可能性があります。
⇒つまり、多数決で決めるということでしょうか?
Sputter氏は、18世紀のフランスの哲学者Condorcetに由来する、コンセンサスに基づいてグループが決定に至ったかどうかのテストを行った。コンドルセットは、陪審制度を正当化するために、独立した立場の個人の過半数が、「罪のある」と「罪のない」との間の決定において正しいとする確率が、グループの大きさとともに増加することを示した。
⇒つまり、人間参考にする意思の数(人の数)が多いほど、自分の判断が正しいと認識してしまう。ということでしょうか?
今や、研究者は、トゲウオの群れで同じことが言えると指摘しています。 Wardは、イトヨの群れと、2つのレプリカを使って、魚の特徴(サイズ、肥満、陰影、スポッティネスなど)は、個体の健康や体力について反映していることを証明しました。例えば、ふっくらとした腹は食物摂取の成功を示すことができ、スポットは寄生虫感染を示す可能性がある。
彼はその後、1~8匹のトゲウオを使って、2つのレプリカフィッシュの中からどちらかを選択させる実験を行いました。レプリカは、トゲウオの群れを使った実験で、魅力的なレプリカと、駄目なレプリカの2つを用意した。トゲウオの数が増えるにつれて、魚はより正確な決定を下したと研究者らは報告する。
⇒魚も人間と同じく、コンセンサスで全体の意思を決める。
正しい判断をする精度は、魚の群れが大きくなるほど、高くなる。
大部分の試行では、ほとんどの魚が魅力的な魚についていった。しかし、コンセンサス法は時には魚を迷わせた。実質的に少数の試験では、魅力的ではないリーダーを追っていました。
・・・・・・・
どうでしょうか?
もし、針のついた餌を食べることが、「駄目な判断」だとしたら、
群れが大きくなればなるほど、釣り難くなりますね。
見えている魚(群れ)は釣れない。というのは、もしかすると、
魚の群れの意思決定が、コンセンサス方法で行われているかも知れません。
沖縄のヒレーカーとかは、フカセつりで見えている群れを狙うと釣るのが難しいけど、
やんばるのかご釣りでは、結構大型バショーカーが釣れていることに関係しているのでしょうか?
※※(Google翻訳で翻訳し、それを私が翻訳したので、間違って解釈しているかも知れません。)
追記
そういえば、フィッシングショーで、松田稔がグレの食い気スイッチについてしゃべっていたことを思い出しました。
「もう、ここ(口)に(餌が)あたっても喰わなんよ。ずっと(撒き餌)まきつづけると、何かが入ったら、急に2,3匹が餌を食いだすんよ。色が変わって、全体が喰いだすんよ。」
下の動画の13:30あたりからです。
これは、群れのリーダーが、餌を食べて、その周りの魚も、食って、群れ全体が正しい行動と思ったのでしょうか?
点と点が薄っすい線で、かすかにつながった気がします。
下が、一応グーグル翻訳をして、すこし手を加えた日本語の文章です。
シドニー大学のアシュリーワード(Ashley Ward)氏は、「トゲウオの群れはより小さな先導者(群れの方向を決める魚)よりも大きい先導者に従う傾向があることが判明しました。実際に私たちの目を惹いたのは、ある種の社会的フィードバックメカニズムによって、群れの規模が拡大するにつれて、このような傾向が高まったことだ」と語った。
ウプサラ大学のDavid Sumpter教授は、「彼らの合意は簡単なルールによって生まれる。 「ある魚は正しい方向に進む。しかし、それと同時に間違いを犯して間違った方向に進む魚もいる。まだ、意思が決まっていない魚は、数の多いほうへ進む。そうやって、一方の道に魚の数が多くなり、残りの魚は数の多いほうへついていく」
⇒つまり、①先導者⇒②先導者を判断する魚⇒③後ろのほうの魚
の順で、群れは方向を決めながら進んでいくということでしょうか?
魚は意思決定を行うときに、前の魚の意思決定を参考にする?
Sumpterは、「全体の意思決定」とは、ひとりひとりの意思決定から決定されて、できる限り効果的にその意思を満たすための意思決定である。 「通常、私たち自身の意思決定について話すとき、誰もが行動の過程についての証拠を提示することが許され、意思決定者が意思決定者の一般的意見を反映するならば合意に達すると我々は言う。これは、1人または非常に少数のグループメンバーによる意思決定とは対照的です。グループメンバーは、自分の意見だけを反映する可能性があります。
⇒つまり、多数決で決めるということでしょうか?
Sputter氏は、18世紀のフランスの哲学者Condorcetに由来する、コンセンサスに基づいてグループが決定に至ったかどうかのテストを行った。コンドルセットは、陪審制度を正当化するために、独立した立場の個人の過半数が、「罪のある」と「罪のない」との間の決定において正しいとする確率が、グループの大きさとともに増加することを示した。
⇒つまり、人間参考にする意思の数(人の数)が多いほど、自分の判断が正しいと認識してしまう。ということでしょうか?
今や、研究者は、トゲウオの群れで同じことが言えると指摘しています。 Wardは、イトヨの群れと、2つのレプリカを使って、魚の特徴(サイズ、肥満、陰影、スポッティネスなど)は、個体の健康や体力について反映していることを証明しました。例えば、ふっくらとした腹は食物摂取の成功を示すことができ、スポットは寄生虫感染を示す可能性がある。
彼はその後、1~8匹のトゲウオを使って、2つのレプリカフィッシュの中からどちらかを選択させる実験を行いました。レプリカは、トゲウオの群れを使った実験で、魅力的なレプリカと、駄目なレプリカの2つを用意した。トゲウオの数が増えるにつれて、魚はより正確な決定を下したと研究者らは報告する。
⇒魚も人間と同じく、コンセンサスで全体の意思を決める。
正しい判断をする精度は、魚の群れが大きくなるほど、高くなる。
大部分の試行では、ほとんどの魚が魅力的な魚についていった。しかし、コンセンサス法は時には魚を迷わせた。実質的に少数の試験では、魅力的ではないリーダーを追っていました。
・・・・・・・
どうでしょうか?
もし、針のついた餌を食べることが、「駄目な判断」だとしたら、
群れが大きくなればなるほど、釣り難くなりますね。
見えている魚(群れ)は釣れない。というのは、もしかすると、
魚の群れの意思決定が、コンセンサス方法で行われているかも知れません。
沖縄のヒレーカーとかは、フカセつりで見えている群れを狙うと釣るのが難しいけど、
やんばるのかご釣りでは、結構大型バショーカーが釣れていることに関係しているのでしょうか?
※※(Google翻訳で翻訳し、それを私が翻訳したので、間違って解釈しているかも知れません。)
追記
そういえば、フィッシングショーで、松田稔がグレの食い気スイッチについてしゃべっていたことを思い出しました。
「もう、ここ(口)に(餌が)あたっても喰わなんよ。ずっと(撒き餌)まきつづけると、何かが入ったら、急に2,3匹が餌を食いだすんよ。色が変わって、全体が喰いだすんよ。」
下の動画の13:30あたりからです。
これは、群れのリーダーが、餌を食べて、その周りの魚も、食って、群れ全体が正しい行動と思ったのでしょうか?
点と点が薄っすい線で、かすかにつながった気がします。
 下が、一応グーグル翻訳をして、すこし手を加えた日本語の文章です。
シドニー大学のアシュリーワード(Ashley Ward)氏は、「トゲウオの群れはより小さな先導者(群れの方向を決める魚)よりも大きい先導者に従う傾向があることが判明しました。実際に私たちの目を惹いたのは、ある種の社会的フィードバックメカニズムによって、群れの規模が拡大するにつれて、このような傾向が高まったことだ」と語った。
ウプサラ大学のDavid Sumpter教授は、「彼らの合意は簡単なルールによって生まれる。 「ある魚は正しい方向に進む。しかし、それと同時に間違いを犯して間違った方向に進む魚もいる。まだ、意思が決まっていない魚は、数の多いほうへ進む。そうやって、一方の道に魚の数が多くなり、残りの魚は数の多いほうへついていく」
⇒つまり、①先導者⇒②先導者を判断する魚⇒③後ろのほうの魚
の順で、群れは方向を決めながら進んでいくということでしょうか?
魚は意思決定を行うときに、前の魚の意思決定を参考にする?
Sumpterは、「全体の意思決定」とは、ひとりひとりの意思決定から決定されて、できる限り効果的にその意思を満たすための意思決定である。 「通常、私たち自身の意思決定について話すとき、誰もが行動の過程についての証拠を提示することが許され、意思決定者が意思決定者の一般的意見を反映するならば合意に達すると我々は言う。これは、1人または非常に少数のグループメンバーによる意思決定とは対照的です。グループメンバーは、自分の意見だけを反映する可能性があります。
⇒つまり、多数決で決めるということでしょうか?
Sputter氏は、18世紀のフランスの哲学者Condorcetに由来する、コンセンサスに基づいてグループが決定に至ったかどうかのテストを行った。コンドルセットは、陪審制度を正当化するために、独立した立場の個人の過半数が、「罪のある」と「罪のない」との間の決定において正しいとする確率が、グループの大きさとともに増加することを示した。
⇒つまり、人間参考にする意思の数(人の数)が多いほど、自分の判断が正しいと認識してしまう。ということでしょうか?
今や、研究者は、トゲウオの群れで同じことが言えると指摘しています。 Wardは、イトヨの群れと、2つのレプリカを使って、魚の特徴(サイズ、肥満、陰影、スポッティネスなど)は、個体の健康や体力について反映していることを証明しました。例えば、ふっくらとした腹は食物摂取の成功を示すことができ、スポットは寄生虫感染を示す可能性がある。
彼はその後、1~8匹のトゲウオを使って、2つのレプリカフィッシュの中からどちらかを選択させる実験を行いました。レプリカは、トゲウオの群れを使った実験で、魅力的なレプリカと、駄目なレプリカの2つを用意した。トゲウオの数が増えるにつれて、魚はより正確な決定を下したと研究者らは報告する。
⇒魚も人間と同じく、コンセンサスで全体の意思を決める。
正しい判断をする精度は、魚の群れが大きくなるほど、高くなる。
大部分の試行では、ほとんどの魚が魅力的な魚についていった。しかし、コンセンサス法は時には魚を迷わせた。実質的に少数の試験では、魅力的ではないリーダーを追っていました。
・・・・・・・
どうでしょうか?
もし、針のついた餌を食べることが、「駄目な判断」だとしたら、
群れが大きくなればなるほど、釣り難くなりますね。
見えている魚(群れ)は釣れない。というのは、もしかすると、
魚の群れの意思決定が、コンセンサス方法で行われているかも知れません。
沖縄のヒレーカーとかは、フカセつりで見えている群れを狙うと釣るのが難しいけど、
やんばるのかご釣りでは、結構大型バショーカーが釣れていることに関係しているのでしょうか?
※※(Google翻訳で翻訳し、それを私が翻訳したので、間違って解釈しているかも知れません。)
追記
そういえば、フィッシングショーで、松田稔がグレの食い気スイッチについてしゃべっていたことを思い出しました。
「もう、ここ(口)に(餌が)あたっても喰わなんよ。ずっと(撒き餌)まきつづけると、何かが入ったら、急に2,3匹が餌を食いだすんよ。色が変わって、全体が喰いだすんよ。」
下の動画の13:30あたりからです。
これは、群れのリーダーが、餌を食べて、その周りの魚も、食って、群れ全体が正しい行動と思ったのでしょうか?
点と点が薄っすい線で、かすかにつながった気がします。
下が、一応グーグル翻訳をして、すこし手を加えた日本語の文章です。
シドニー大学のアシュリーワード(Ashley Ward)氏は、「トゲウオの群れはより小さな先導者(群れの方向を決める魚)よりも大きい先導者に従う傾向があることが判明しました。実際に私たちの目を惹いたのは、ある種の社会的フィードバックメカニズムによって、群れの規模が拡大するにつれて、このような傾向が高まったことだ」と語った。
ウプサラ大学のDavid Sumpter教授は、「彼らの合意は簡単なルールによって生まれる。 「ある魚は正しい方向に進む。しかし、それと同時に間違いを犯して間違った方向に進む魚もいる。まだ、意思が決まっていない魚は、数の多いほうへ進む。そうやって、一方の道に魚の数が多くなり、残りの魚は数の多いほうへついていく」
⇒つまり、①先導者⇒②先導者を判断する魚⇒③後ろのほうの魚
の順で、群れは方向を決めながら進んでいくということでしょうか?
魚は意思決定を行うときに、前の魚の意思決定を参考にする?
Sumpterは、「全体の意思決定」とは、ひとりひとりの意思決定から決定されて、できる限り効果的にその意思を満たすための意思決定である。 「通常、私たち自身の意思決定について話すとき、誰もが行動の過程についての証拠を提示することが許され、意思決定者が意思決定者の一般的意見を反映するならば合意に達すると我々は言う。これは、1人または非常に少数のグループメンバーによる意思決定とは対照的です。グループメンバーは、自分の意見だけを反映する可能性があります。
⇒つまり、多数決で決めるということでしょうか?
Sputter氏は、18世紀のフランスの哲学者Condorcetに由来する、コンセンサスに基づいてグループが決定に至ったかどうかのテストを行った。コンドルセットは、陪審制度を正当化するために、独立した立場の個人の過半数が、「罪のある」と「罪のない」との間の決定において正しいとする確率が、グループの大きさとともに増加することを示した。
⇒つまり、人間参考にする意思の数(人の数)が多いほど、自分の判断が正しいと認識してしまう。ということでしょうか?
今や、研究者は、トゲウオの群れで同じことが言えると指摘しています。 Wardは、イトヨの群れと、2つのレプリカを使って、魚の特徴(サイズ、肥満、陰影、スポッティネスなど)は、個体の健康や体力について反映していることを証明しました。例えば、ふっくらとした腹は食物摂取の成功を示すことができ、スポットは寄生虫感染を示す可能性がある。
彼はその後、1~8匹のトゲウオを使って、2つのレプリカフィッシュの中からどちらかを選択させる実験を行いました。レプリカは、トゲウオの群れを使った実験で、魅力的なレプリカと、駄目なレプリカの2つを用意した。トゲウオの数が増えるにつれて、魚はより正確な決定を下したと研究者らは報告する。
⇒魚も人間と同じく、コンセンサスで全体の意思を決める。
正しい判断をする精度は、魚の群れが大きくなるほど、高くなる。
大部分の試行では、ほとんどの魚が魅力的な魚についていった。しかし、コンセンサス法は時には魚を迷わせた。実質的に少数の試験では、魅力的ではないリーダーを追っていました。
・・・・・・・
どうでしょうか?
もし、針のついた餌を食べることが、「駄目な判断」だとしたら、
群れが大きくなればなるほど、釣り難くなりますね。
見えている魚(群れ)は釣れない。というのは、もしかすると、
魚の群れの意思決定が、コンセンサス方法で行われているかも知れません。
沖縄のヒレーカーとかは、フカセつりで見えている群れを狙うと釣るのが難しいけど、
やんばるのかご釣りでは、結構大型バショーカーが釣れていることに関係しているのでしょうか?
※※(Google翻訳で翻訳し、それを私が翻訳したので、間違って解釈しているかも知れません。)
追記
そういえば、フィッシングショーで、松田稔がグレの食い気スイッチについてしゃべっていたことを思い出しました。
「もう、ここ(口)に(餌が)あたっても喰わなんよ。ずっと(撒き餌)まきつづけると、何かが入ったら、急に2,3匹が餌を食いだすんよ。色が変わって、全体が喰いだすんよ。」
下の動画の13:30あたりからです。
これは、群れのリーダーが、餌を食べて、その周りの魚も、食って、群れ全体が正しい行動と思ったのでしょうか?
点と点が薄っすい線で、かすかにつながった気がします。
Posted by siosaikouen at 18:35│Comments(0)
│魚に関する英語の記事
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。